リカバリーとは
リカバリーを日本語に訳すと「回復」「復旧」になると思いますが、精神保健領域では以下のように捉えられています。
アンソニー(Anthony, W.)
・精神疾患をもつ者が、症状や障害が継続したとしても人生の新しい意味や目的を見出し、充実した人生を生きていくプロセスである
ディーガン(Deegan, P.)
・リカバリーは、生活の仕方、姿勢、日々の課題への取り組み方である
・リカバリーは、完全に直線的な過程ではない
・リカバリーは、課題に立ち向かうことが求められる
・リカバリーは、新たな目標を再構築する
このように、リカバリーは病気や障害から回復した結果ではなく、その「過程」を重視することを押さえておきましょう。
パーソナルリカバリー
リカバリーは従来、治療者視点に立った症状の改善と機能の回復という意味での「臨床的リカバリー」でしたが、当事者視点に立った客観的な回復(生活、就労など)や主観的な回復(将来への希望、自分らしさ、他者との関係など)を合わせた「パーソナルリカバリー」という概念があります。
つまり、パーソナルリカバリーとは、障害があっても希望をもって新たな人生を再発見し、主体的に生きることです。
元気回復行動プランWRAP
元気回復行動プラン(WRAP:Wellness Recovery Action Plan)は、リカバリーのために必要な希望や主体性などを学び、自分でつくるセルフケアプランです。
自身も精神障害を持つコープランド(Copeland,M.E.)を中心に、アメリカの精神障害のある人たちによって作られました。
WRAPでは以下の6つプランを作成します。
・引き金と対応プラン
・注意サインと対応プラン
・調子が悪くなっているときのサインと対応プラン
・クライシスプラン
・クライシス後のプラン
過去問
第22回 問題39
次の記述のうち、ディーガン(Deegan, P.)が述べるリカバリーの内容として、正しいものを2つ選びなさい。
1 病気になる前の状態に戻る。
2 新たな目的を再構築する。
3 目標に向けて直線的に前進する。
4 課題に立ち向かうことが求められる。
5 回復した結果を重視する。
1 病気になる前の状態に戻る。
間違いです。これはリカバリーではありません。
2 新たな目的を再構築する。
正しいです。
3 目標に向けて直線的に前進する。
間違いです。ディーガンは、「リカバリーは、完全に直線的な過程ではない」と述べています。
4 課題に立ち向かうことが求められる。
正しいです。
5 回復した結果を重視する。
間違いです。「結果」ではなく「過程」を重視します。
第24回 問題46
次の記述のうち、精神障害がある者のリカバリーについての説明として、適切なものを1つ選びなさい。1 全ての人が同じリカバリーの過程を経る。2 本人が自由に挑戦できるよう、支援者が責任を負う。3 本人の障害の部分に焦点を当てる。4 希望はリカバリーを支える原動力となる。5 身体的状況を切り離し、精神的な回復を図る。
選択肢4が正解です。
第25回 問題33、34、35
次の事例を読んで、問題33から問題35までについて答えなさい。
〔事 例〕
Jさん(55歳、男性)は、高校生の時に統合失調症を発症したが、今は病状も落ち着き、通院しながらアパートで一人暮らしをしている。Jさんは、3年ほど前から、K精神保健福祉士が勤めている地域活動支援センターで週に1~2日過ごしているほか、昨年からは月に1度保健所で開かれている「精神保健福祉を考える集い」(以下「集い」という。)に参加している。「集い」では精神障害当事者のほか、病院や地域の精神保健福祉士や地域住民など20名ほどが集まり、その月の出来事などを語り合っている。「集い」の代表は統合失調症を経験したLさんであり、「集い」の運営や事務を行っている。人との交流の少ないJさんにとってはいろいろな人と出会う大切な機会となっている。ある日、K精神保健福祉士は暗い表情をしたJさんから、「Lさんが県外に転居することになった。Lさんがいなくなったら『集い』はどうなってしまうのだろう」と消え入るような声で相談を受けた。(問題33)
Lさんの転居後約1年の間に、様々な広報活動の効果もあり、「集い」は精神障害当事者の参加が増え、病気を抱えながら生活する日々の出来事が前向きに捉え直されたり、元気づけられたり、また地域住民との間で共有される場面が多くなった。やがて「集い」には精神科病院から、「ここで話されているようなことを入院中の方とも話してほしい」という依頼が来るようになった。Jさんも数回精神科病院で入院中の方と話をした。ある日JさんはK精神保健福祉士に、「入院中の方に退院後の生活や自分の体験を話すことで自分が人の力になれるように感じた。精神科病院を訪問した仲間たちの間で、『このような活動を続けるために精神障害当事者の会を立ち上げたい』と話しているので相談に乗ってほしい」と伝えた。(問題34)
K精神保健福祉士は、地域活動支援センターで一人静かに時を過ごし、「集い」に参加し始めた頃のJさんを思い出し、「Jさんは変わられましたね」と声をかけた。(問題35)
- 問題33 次の記述のうち、この時のK精神保健福祉士の対応として、適切なものを2つ選びなさい。
1 Jさんに、Lさんの後を継ぐように勧める。
2 JさんのためにLさんに連絡を取り、方針を決めてもらう。- 3 Jさんの「集い」に対するこれまでの気持ちを聞き取る。
4 Jさんのために「集い」に参加し「集い」が継続するように、力を尽くす。
5 Jさんに、他の参加者と一緒に「集い」のこれからを考えていけるよう促す。
選択肢3と5が正解です。
- 問題34 次のうち、Jさんたちが始めようとしている会の活動として、適切なものを1つ選びなさい。
1 コンサルテーション- 2 スーパービジョン
3 ソーシャルアクション- 4 ピアサポート
- 5 アファーマティブアクション
選択肢4が正解です。
問題35 次のうち、K精神保健福祉士の発言の背景にある考え方として、適切なものを1つ選びなさい。
1 リカバリー
2 コ・プロダクシ ョン
3 コンピテンス
4 ライフヒストリー
5 ワーカビリティ
選択肢1が正解です。
第27回 問題38
次の記述のうち、パーソナルリカバリーの説明として、正しいものを1つ選びなさい。
1 激しい症状が治まり、薬を必要としない状態になること。
2 支援者がクライエントの利益のために、本人の意思に関わりなく判断すること。
3 支援者が定めた方針に、クライエントが従うこと。
4 専門職が自らの支援やその役割について責任をもって説明を行うこと。
5 障害があっても希望をもって新たな人生を再発見し、主体的に生きること。
選択肢5が正解です。
第24回 問題78、79、80
次の事例を読んで、問題78から問題80までについて答えなさい。
〔事 例〕
Aさん(30歳、男性)は、21歳の時に統合失調症と診断され、母親と二人で住む市内にあるX精神科病院に入院した。しばらくして症状はようやく落ち着いたが、母親は自宅への退院に難色を示し、他の退院後の受入先も確保できず退院の話は進まなかった。そのうちAさんの退院意欲が減退したこともあり、入院は長期化した。
Aさんは28歳の時、地域で生活する精神障害当事者と対話できるX精神科病院内のプログラムに参加した。そこでAさんは退院意欲が喚起され、病院のB精神保健福祉士に、「退院して自宅に戻りたい」と相談を持ちかけた。B精神保健福祉士は、Aさんとの面接に加えて母親との面接を設定した。面接で母親は、「病気のことがよく分からないし、また入院前の、あの大変な状況に戻っても対応できる自信がない」と語り、自宅への退院に後ろ向きであった。B精神保健福祉士は、家族を対象に専門家が実施するX精神科病院内の家族の感情表出に着目したプログラムへの参加を勧めた。(問題78)
プログラムへの参加を通して、母親はAさんの自宅への退院に前向きになり、様々な人の支援を受けながらAさんは自宅へ退院した。しかし退院後間もなく、母親は体調を崩して1週間ほど入院となり、自宅でAさんの身の回りの世話をできる人がいなくなった。Aさんは生活能力の低下もあいまって心細さを強く訴えるようになったため、「障害者総合支援法」に規定される、短期間の入所により食事や入浴の提供などを行うサービスを利用することとした。(問題79)
母親の退院後しばらくして、Aさんは自宅に戻った。B精神保健福祉士の勧めでY地域活動支援センターに通い、徐々に地域での生活を楽しむようになった。Y地域活動支援センターでは、米国で精神障害当事者が開発したリカバリーに向けたプログラムが行われていた。入院中に知り合ったCさんに誘われてAさんもそのプログラムに参加した。そこで、自分のこれからの人生を考えられるようになった。(問題80)
(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
次のうち、Aさんの母親が参加したプログラムとして、適切なものを1つ選びなさい。
1 心理教育
2 社会生活技能訓練(SST)
3 包括型地域生活支援プログラム(ACT)
4 ピアカウンセリング
5 森田療法
選択肢1が正解です。母親は「病気のことがよくわからない」と話しており、心理教育によって統合失調症の特徴や接し方を学ぶことが想定されます。
次の記述のうち、Aさんが利用したサービスの説明として、正しいものを1つ選びなさい。
1 利用者の外出時における移動中の介護を行う。
2 保健所が利用申請の窓口である。
3 夜間もサービスを提供する。
4 訓練等給付に基づくサービスである。
5 定期的な巡回訪問を実施する。
選択肢3が正解です。事例では短期入所を利用したと思われます。
Aさんが参加したプログラムに関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
1 「私たちは一人ぼっちではない(We are not alone)」を合言葉とした。
2 精神障害当事者が中心となって実施する。
3 支援者と共同で創出した働く場が起源である。
4 困難な時の対処方法について、プランをあらかじめ作成する。
5 匿名での参加が原則である。
米国で精神障害当事者が開発したリカバリーに向けたプログラムということで、元気回復行動プランWRAPのことだと思われます。
1 「私たちは一人ぼっちではない(We are not alone)」を合言葉とした。
誤りです。これはクラブハウスモデルの内容です。
2 精神障害当事者が中心となって実施する。
正しいです。元気回復行動プランWRAPは精神障害者当事者が中心となって実施します。
3 支援者と共同で創出した働く場が起源である。
誤りです。これはソーシャルファームの内容です。ソーシャルファームは障害者など労働市場で不利な立場にある人のために仕事を生み出したり、支援付きの雇用の機会を提供するビジネスです。
4 困難な時の対処方法について、プランをあらかじめ作成する。
正しいです。WRAPではこれを含む6つのプランを作成します。
5 匿名での参加が原則である。
誤りです。匿名での参加といえばアルコホリークス・アノニマスなどの自助グループです。
第18回 問題75
次の記述のうち、元気回復行動プラン(WRAP)に関する説明として、正しいものを1つ選びなさい。1 自らの意思では受診が困難な精神障害者に対し、支援者が暮らす場に出向いて支援する際の活用を目的に作成された。2 アメリカの援助付き雇用の方法を導入して、支援者が働く場に出向いて支援する際に活用することを目的に作成された。3 ヨーロッパで精神科病院が縮小された後、地域の中で精神障害者が働く場を創出する際に活用されたことに起源がある。4 インフォーマルなサポートとフォーマルなサポートを織り交ぜながらネットワークを構築する方法として活用される。5 精神障害を有する当事者の間で考案されたもので、ファシリテーターとして活動する人の養成が行われている。
1 自らの意思では受診が困難な精神障害者に対し、支援者が暮らす場に出向いて支援する際の活用を目的に作成された。
誤りです。これはアウトリーチの内容です。
2 アメリカの援助付き雇用の方法を導入して、支援者が働く場に出向いて支援する際に活用することを目的に作成された。
誤りです。これはジョブコーチの内容です。
3 ヨーロッパで精神科病院が縮小された後、地域の中で精神障害者が働く場を創出する際に活用されたことに起源がある。
これはソーシャルファームの内容です。
4 インフォーマルなサポートとフォーマルなサポートを織り交ぜながらネットワークを構築する方法として活用される。
誤りです。これはソーシャルサポートネットワークの内容です。
5 精神障害を有する当事者の間で考案されたもので、ファシリテーターとして活動する人の養成が行われている。
これが正解です。
次の記事
次は、医療リワークです。



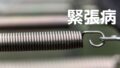
コメント