障害福祉における重要な理念や概念を見ていきましょう。
ノーマライゼーション3人衆
バンク-ミケルセン
ノーマライゼーションを世界で初めて提唱したのはデンマークのニルス・エリク・バンク-ミケルセンです。

1950年代、デンマークでは知的障害者が施設に隔離されていました。
バンク-ミケルセン(Bank-Mikkelsen,N.)は、劣悪な環境の施設に収容されている知的障害児者の処遇に心を痛め、1951年に発足した知的障害者の親の会の活動に共鳴し、そのスローガンが法律として実現するように尽力しました。
それによって1959年 知的障害者福祉法ができます。
.png)
彼は若いころナチスの収容所に収監されていたことがあったんだ。そこから奇跡的に生き延びて公務員として障害者施設で働くようになったんだ。その時、知的障害者が暮らしている施設が、まるでナチスの収容所のようだと嘆いたと言われていて、ノーマライゼーションの理念が生み出されるキッカケになったんだ。
この法律はノーマライゼーション法とか1959年法とも呼ばれていますが、この法律には彼が知的障害者の親の会の要請を文章化する過程で生まれたノーマライゼーションの理念が盛り込まれ、世界で初めてノーマライゼーションという言葉が法律に用いられ、明文化されました。
つまり、ノーマライゼーションの理念は、もともとは「障害のある人にも、障害のない人と同じ生活を」というのが出発点だったのです。
日本の障害福祉の始まりは入所施設から、でしたが、ノーマライゼーションの始まりも入所施設からなのです。
障害福祉の歴史は入所施設の歴史でもあります。1950年代は「施設症」による弊害が指摘された始めた時期でもあり、ノーマライゼーションの理念の浸透に伴って、脱施設化の流れも加速していきます。
.png)
バンク-ミケルセンは「ノーマライゼーションの父」と呼ばれているよ。
ノーマライゼーションの発祥はデンマークであることも覚えておきましょう。
スウェーデンではありません。
ベンクト・ニィリエ
スウェーデン知的障害児者連盟のニィリエ(Nirje,B)は、バンク‐ミケルセンのノーマライゼーションの理念に影響を受け、英文に訳して広く国際的に広めました。
1960年、ニィリエは「知的障害者は、ノーマルなリズムにしたがって生活し、ノーマルな成長段階を経て、一般の人々と同等のノーマルなライフサイクルを送る権利がある」とし、ノーマライゼーションを「8つの原理」に分けて示しています。
覚える必要はありませんが、さらっと目を通しておいてください。
<ノーマライゼーション8つの原理>
障害のある人もない人も以下の8つの原理に沿った生活が保障されるべきとしています。
1.ノーマライゼーションとは、一日の普通のリズム
一日一日を一定のリズムで過ごせるような環境を作り出すべきという考え方です。
2.ノーマライゼーションとは、一週間の普通のリズム
平日は職場や学校などで活動し、週末には自宅で休日を過ごすというような一週間のリズムで過ごせるような環境を作り出すべきという考え方です。
3.ノーマライゼーションとは、一年の普通のリズム
一年を通した季節の変化、季節ごとのイベントなど、障害の有無でこのようなイベントの参加の機会を奪われてはいけないという考え方です。
4.ノーマライゼーションとは、当たり前の成長の過程をたどること
誰もが生まれてから、幼少期、青年期、老年期と辿っていく中で、それぞれのライフステージに合った生活が保障されるべきという考え方です。
幼少期なら家族と遊びに行ったり、青年期には会社で働いたり家庭を持ったり等々ですね。
5.ノーマライゼーションとは、自由と希望を持ち、周りの人もそれを認め、尊重してくれること
うまく言葉で伝えることができない人にも、その人の意見や希望が尊重され非難されることのない社会の仕組みを整えていくべきという考え方です。
6.ノーマライゼーションとは、男性、女性どちらもいる世界に住むこと
社会の中には、大人や子供、男性や女性が一緒に生きています。
男女を分離するのではなく協力し合える環境を作るべきという考え方です。
7.ノーマライゼーションとは、平均的経済水準を保障されること
基本的な公的財政援助や最低賃金保障など、経済的な安定が保障されるべきという考え方です。
8.ノーマライゼーションとは、普通の地域の普通の家に住むこと
障害のある人とない人で住む家や環境に違いがあるのは好ましくなく、入所施設等の環境を一般的な家に近づけていくべきという考え方です。
.png)
バンク-ミケルセンはノーマライゼーション「生みの親」、ニィリエは「育ての親」だね。
ヴォルフェンスベルガー
ヴォルフェンスベルガー(Wolfensberger, W.)は、文化的、社会的役割としてのノーマライゼーションであるソーシャルロールバロリゼーション(SRV:social role valorization)を提唱します。
ソーシャルロールバロリゼーションは、直訳すれば「社会的役割に価値(バリュー)を与える(バロライズする)」という事で、「障害のある人にも価値ある社会的役割を!」という概念です。
詳細は以下の記事で。

過去問
第21回 問題23
次の記述のうち、ヴォルフェンスベルガー(Wolfensberger, W.)が新たに提唱したノーマライゼーションの理念として、適切なものを1 つ選びなさい。
1 障害がある人たちに、障害のない人々と同じ生活条件をつくり出す。
2 社会で主流となっている、毎日の生活条件に近い環境での暮らしを目指す。
3 自己決定と選択権が最大限尊重されている限り、人格的には自立しているとみなす。
4 社会に完全かつ効果的に参加し、社会に受け入れられるようにする。
5 社会的に価値を低められている人々に、社会的役割をつくり出す。
選択肢5が正解です。
第15回 問題25
ノーマライゼーションに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 デンマークで1950年代に設立された知的障害者本人の会であるピープルファーストの運動に端を発し、スウェーデン、アメリカ、カナダで発展した。
2 ノーマライゼーションの理念に基づき, 1960年代から1970年代にかけて日本をはじめとした先進諸国では、急速に脱施設化の政策が進められた。
3 障害者は、障害のない人と変わらない普通の生活を送ることができるように、障害者を訓練し、社会に適応させていくことの重要性を唱えた理念である。
4 ノーマライゼーションの目的は、障害者を収容してきた施設を解体することである。
5 ニイリエは、「知的障害者の日常生活をできるだけ社会の主流となっている規範や形態に近づけるようにすること」とし、「8つの原理」を定めた。
1 デンマークで1950年代に設立された知的障害者本人の会であるピープルファーストの運動に端を発し、スウェーデン、アメリカ、カナダで発展した。
間違いです。ピープルファーストというのは、1973年アメリカで知的障害のある当事者が「知的障害者」とレッテルを貼られることに対して「私たちは障害者である前に人間だ」と発言したことがきっかけで始まりました。
2 ノーマライゼーションの理念に基づき, 1960年代から1970年代にかけて日本をはじめとした先進諸国では、急速に脱施設化の政策が進められた。
間違いです。1960年に日本で制定された精神薄弱者福祉法によって、世界的に脱施設が叫ばれ始めた中で、それに逆行するように施設が全国に広がるきっかけになりました。
3 障害者は、障害のない人と変わらない普通の生活を送ることができるように、障害者を訓練し、社会に適応させていくことの重要性を唱えた理念である。
障害者を訓練して社会に適応させるというのはノーマライゼーションの理念とは真逆です。
4 ノーマライゼーションの目的は、障害者を収容してきた施設を解体することである。
間違いです。施設解体が目的ではありません。施設も必要です。必要悪と言われても。
5 ニイリエは、「知的障害者の日常生活をできるだけ社会の主流となっている規範や形態に近づけるようにすること」とし、「8つの原理」を定めた。
これが正解です。
第26回 問題22
- 次のうち、ソーシャルロール・バロリゼーションを提唱した人物として、正しいものを1つ選びなさい。
1 ニィリエ(Nirje, B.)
2 ビアーズ(Beers, C.)
3 ヴォルフェンスベルガー(Wolfensberger, W.)
4 ラップ(Rapp, C.)
5 バンク-ミケルセン(Bank-Mikkelsen, N.)
選択肢3が正解です。
次の記事
次は、セルフエスティーム&セルフエフィカシーについて。

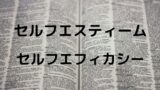


コメント