精神障害者の権利擁護
3障害の中でも身体障害者と知的障害者は、戦後まもなく身体障害者福祉法および精神薄弱者福祉法によって不十分ながらも権利が護られ、心身障害者対策基本法の成立によって身体障害者と知的障害者対策が一元的に推進されることとなりました。
しかし精神障害者に至っては戦後から長らく法的な規定すらなく、1993年に心身障害者対策基本法が障害者基本法となり初めて精神障害者が法的に規定されるに至り、その権利擁護の歴史は始まったばかりです。
2014年の障害者権利条約の批准によって「合理的配慮」や「社会的障壁の除去」など、3障害全体としては権利擁護が進んできましたが、精神障害者に関しては根強く残る差別意識が、その進展を遅らせていると言わざるを得ません。
1964年に起こったライシャワー事件を契機として精神障害者に対する事実上の隔離政策が進められ、1984年の宇都宮病院事件で全国的に精神障害者の権利が蹂躙されていることが明らかになりました。
それから半世紀近く経過した現在でも、精神障害者本人の同意によらない強制的な入院形態(医療保護入院、措置入院、応急入院)の存在や、障害者総合支援法に規定される「精神通院医療」が都道府県による指定を受ける必要があることなど、精神障害者に対する差別や偏見の歴史の名残が今でも見受けられます。
このように精神障害者の権利擁護の歴史は、現在でも発展途上です。
ここからは、相談援助を行う上での権利擁護の形「アドボカシー」を見ていきましょう。
アドボカシーは「権利擁護」や「代弁」などと訳されますが、その機能には様々あります。
.png)
アドボカシー(advocacy)は、ラテン語の「voco(声を上げる)」に由来するらしいね。
アドボカシーの5機能
介入機能
介入機能は、ソーシャルワーカーの理念と組織・制度の問題を結び付けるために、クライエント集団と地域福祉政策とを結び付ける機能です。
発見機能
発見機能は、クライエントの置かれている環境や状況に対して、問題を見付け出し提起する機能で、クライエント自身に自らのニーズと権利に気づきをもたらすことができます。
調整(仲介)機能
調整機能は、制度や組織との仲介者・媒介者として調整する機能です。
対決機能、代弁機能
対決機能、代弁機能は、制度や組織の壁に対して、クライエントの利益のために代弁する機能です。
.png)
例えば、購入した商品にクレームを言いたいけどうまく伝えられないクライエントの代わりに、お店に苦情を言うとかだね。
変革機能
変革機能は、法律や制度に働きかけて、社会的変革を起こす機能です。例えば、生活保護制度の設計について訴訟を起こして変革を起こすとかですね。
さらに近年では、これら5つの機能以外に、情報提供機能、教育・啓発機能なども挙げられています。
過去問
第21回 問題28
次の記述のうち、精神保健福祉士が行うアドボカシーにおける介入機能の説明として、適切なものを1つ選びなさい。
1 ソーシャルワーカーの理念と組織・制度の問題を結び付けるために、クライエント集団と地域福祉政策とを結び付ける。
2 日常的なジレンマを抱えながらも、弁護や変革を主体的に推進する。
3 クライエントの置かれている環境や状況に対して、問題を見付け出し提起する。
4 制度や組織との仲介者・媒介者として、個別の問題を扱う。
5 制度や組織の壁に対して、専門職としては中立を保ちながらも、クライエントの利益のために代弁する。
1 ソーシャルワーカーの理念と組織・制度の問題を結び付けるために、クライエント集団と地域福祉政策とを結び付ける。
これが正解です。
2 日常的なジレンマを抱えながらも、弁護や変革を主体的に推進する。
これは「変革機能」の説明です。
3 クライエントの置かれている環境や状況に対して、問題を見付け出し提起する。
これは「発見機能」の説明です。
4 制度や組織との仲介者・媒介者として、個別の問題を扱う。
これは「調整(仲介)機能」の説明です。
5 制度や組織の壁に対して、専門職としては中立を保ちながらも、クライエントの利益のために代弁する。
これは「対決機能」の説明です。アドボケイターは中立ではなく弱者の立場に立って行動します。
第21回 問題39
次の記述のうち、ソーシャルワークにおける権利擁護の中の代弁機能に当たるものとして、正しいものを 1 つ選びなさい。
1 風呂に入っておらず衛生の保持ができていない子どもがいたため、保護者面談で状況を把握した。
2 購入した商品の不満をうまく伝えられない通院患者から依頼を受けて、消費生活センターに同行した。
3 精神科の入院患者に対し、精神医療審査会の役割と利用の仕方について学習会を開催した。
4 被災者に対する医療費減免に関する制度の存続を求めて、関係自治体に対し話合いを求めた。
5 金銭管理に困難のある精神障害者の家族に対し、日常生活自立支援事業とその窓口を伝えた。
1 風呂に入っておらず衛生の保持ができていない子どもがいたため、保護者面談で状況を把握した。
これは「発見機能」の説明です。
2 購入した商品の不満をうまく伝えられない通院患者から依頼を受けて、消費生活センターに同行した。
これが正解、「代弁機能」です。
3 精神科の入院患者に対し、精神医療審査会の役割と利用の仕方について学習会を開催した。
これは「情報提供機能」の説明です。
4 被災者に対する医療費減免に関する制度の存続を求めて、関係自治体に対し話合いを求めた。
これは「変革機能」の説明です。
5 金銭管理に困難のある精神障害者の家族に対し、日常生活自立支援事業とその窓口を伝えた。
これは「情報提供機能」の説明です。
第22回 問題49、50、51
次の事例を読んで、問題49から問題51までについて答えなさい。
〔事 例〕
Kさん(26歳、女性)は大学卒業後Y社に就職した。
配属された部署は残業が多く忙しい職場であった。
直属のL上司はKさんを熱心に指導した。
生真面目なKさんは、L上司の期待に応えようと、自宅に仕事を持ち帰って仕上げるように心がけた。
そのため、仕事が頭から離れず、寝てもすぐに目が覚め、食事も砂を噛んでいるようになっていった。
体調の悪さを自覚したKさんは、社内報に掲載されていたY社が契約している従業員支援プログラム(EAP)機関のことを思い出し、相談に行った。
そこで、Kさんは担当のM精神保健福祉士に、「他の社員に迷惑が掛かるから休めない」「眠れなくてつらい」「このまま消えたい」と涙ながらに訴えた。
M精神保健福祉士は、「よくここまで耐えてこられましたね」とねぎらった上で、次のように提案した。(問題 49)
数日後、KさんはZ精神科病院を受診し、うつ病と診断され入院することとなった。
1か月を経過した頃、Kさんは面会に来たM精神保健福祉士へ、「主治医が退院を許可してくれない。休んでしまった分、早く穴埋めをしたいのに」と訴えた。
面会の1週間後、M精神保健福祉士は、主治医とKさんとL上司とで退院について協議した。
そこで、M精神保健福祉士は次のことを提案した。(問題 50)
後日、入院中であったKさんは、精神科デイケアを体験利用した。
そこでは自分と同じような状況にある利用者と交流して、焦っているのは自分だけではないと感じた。
退院後、精神科デイケアを利用し始めた。
3か月後、M精神保健福祉士は、デイケアスタッフ、主治医、L上司、Kさんと仕事に関して話し合った。
従業員に業務負荷を強く感じさせる労働環境の改善も必要だと、L上司も考えるようになった。
Kさんは負荷の少ない配慮された環境で仕事を再開した。
それから数か月たった頃、M精神保健福祉士は労働環境の改善が必要と考え、L上司に「働き方を考える研修会」の実施を提案した。
そこで、Kさんは体験談を語った。(問題 51)
研修会の後、KさんはM精神保健福祉士に、「初めは、今までのように働けない自分を弱い人間だと感じていた。でも、同じ病の人と出会い、体が壊れるまで働くのは個人にとっても会社にとっても良くないと、今は思う」と語った。
問題49 次のうち、この時点でM精神保健福祉士が提案した内容として、適切なものを1つ選びなさい。
1 入院を勧める。
2 転職を勧める。
3 気分転換として旅行を勧める。
4 受診を勧める。
5 パワーハラスメントで訴えるよう勧める。
これは、選択肢4が正解です。
問題50 次のうち、この時点でM精神保健福祉士が提案した内容として、適切なものを 1 つ選びなさい。
1 「職場適応訓練制度を利用してはどうでしょうか」
2 「就労定着支援事業を利用してはどうでしょうか」
3 「リワークプログラムを利用してはどうでしょうか」
4 「ストレスチェックを受けてはどうでしょうか」
5 「職業評価を受けてはどうでしょうか」
選択肢3が正解です。
問題51 次のうち、この場面において、M精神保健福祉士が果たした役割として、適切なものを1つ選びなさい。
1 スーパーバイザー
2 アドボケーター
3 エバリュエーター
4 メディエーター
5 ファシリテーター
これは、選択肢2が正解です。
M精神保健福祉士はL上司に研修会の実施などを提案していますので、アドボケイターとしての役割を果たしています。
第23回 問題27
精神障害者の権利擁護に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
1 インフォームドコンセントとは、必要だと考えられる治療や検査の方法について、十分な説明をすることである。
2 リーガルアドボカシーとは、障害者自らが、法的な面から権利を主張する活動のことである。
3 援助の記録は、事実の経過や根拠を証明する資料として、権利擁護に貢献するものである。
4 ピアアドボカシーとは、地域の中で障害者が当たり前の生活を営めるように、市民参画型の活動を展開することである。
5 合理的配慮とは、障害者が他の者と平等に全ての人権や基本的自由を享有するための、必要かつ適当な変更や調整のことである。
1 インフォームドコンセントとは、必要だと考えられる治療や検査の方法について、十分な説明をすることである。
間違いです。インフォームドコンセントは、治療や検査の十分な説明をし、合意の上で治療方法を決めることです。
「コンセント=合意」です。
2 リーガルアドボカシーとは、障害者自らが、法的な面から権利を主張する活動のことである。
間違いです。法的な面から権利を主張するのではなく、権利の主張を法的な面から解決していくことです。
3 援助の記録は、事実の経過や根拠を証明する資料として、権利擁護に貢献するものである。
正しいです。
4 ピアアドボカシーとは、地域の中で障害者が当たり前の生活を営めるように、市民参画型の活動を展開することである。
間違いです。ピアアドボカシーは課題を抱える仲間が協力して行うアドボカシーです。
5 合理的配慮とは、障害者が他の者と平等に全ての人権や基本的自由を享有するための、必要かつ適当な変更や調整のことである。
正しいです。
第22回 問題28
精神科病院で精神保健福祉士が行う人権擁護に関する次の記述のうち、最も適切なものを 1 つ選びなさい。
1 「退院はさせないでください」という家族からの求めに応じ、患者に入院の継続を勧める。
2 「もう歳だから」と退院を諦めている長期入院の患者に対して、退院の動機づけを行う。
3 「もう家に帰ります」と突然怒り出した患者を心配し、隔離室に入室させる。
4 「迷惑電話で困っている」という近所の店舗からの苦情を受け、患者が電話をかける機会を制限する。
5 「二人だけで面会させてください」と希望する患者の病状を面会時に判断して、面会に立ち会う。
選択肢2が正解です。
第24回 問題36
- Bさん(30歳、女性、統合失調症)は、週に4日、配送センターで仕分業務に従事して3年目となる。利用する障害者就業・生活支援センターのC就労支援担当者(精神保健福祉士)を訪れ、「配送センターの所長に、繁忙期は勤務日数を増やし、1日8時間勤務できないと雇用継続は難しいと言われた。これ以上働くと体調が不安で、通院する時間もなくなる。仕事は辞めたくない。でも、怖くて何も言えなかった」と訴えた。そこで、C就労支援担当者はBさんとの合意を得て、配送センターを訪問して所長に話をした。
次のうち、この場面でC就労支援担当者が果たした役割として、正しいものを1つ選びなさい。
1 インフォームドコンセント
2 アドボカシー
3 リスクマネジメント
4 セカンドオピニオン
5 アカウンタビリティ
選択肢2が正解です。事例ではC就労支援担当者がBさんの権利を代弁しています。
第25回 問題28
- 次の記述のうち、精神保健福祉士が行う権利擁護における発見機能として、適切なものを1つ選びなさい。
1 生活費の管理に課題を抱えるクライエントに対し、日常生活自立支援事業の活用を促す。
2 退院後に単身生活を控えているクライエントに対し、アパートの物件情報を提供する。
3 ソーシャルワークの理念と組織・制度の問題を結び付けるために、クライエント集団と地域福祉政策とを結び付ける。
4 市民を対象とした精神保健福祉講座の運営を通して、精神障害に対する理解を求める。
5 長期入院にあるクライエントに対し、地域生活のイメージを描けるような働きかけを行う。
1 生活費の管理に課題を抱えるクライエントに対し、日常生活自立支援事業の活用を促す。
これは調整機能です。
2 退院後に単身生活を控えているクライエントに対し、アパートの物件情報を提供する。
これは情報提供機能です。
3 ソーシャルワークの理念と組織・制度の問題を結び付けるために、クライエント集団と地域福祉政策とを結び付ける。
これは介入機能です。
4 市民を対象とした精神保健福祉講座の運営を通して、精神障害に対する理解を求める。
これは教育・啓発機能です。
5 長期入院にあるクライエントに対し、地域生活のイメージを描けるような働きかけを行う。
これが正解、発見機能です。クライエント自身に自らのニーズと権利に気づきをもたらす機能です。
第26回 問題27
- 次の記述のうち、精神保健福祉士が行う権利擁護の調整機能に当たるものとして、適切なものを1つ選びなさい。
1 生活に困窮して相談支援事業所を訪れた人に、生活困窮者自立支援事業の情報を提供する。
2 投票に行けない人々が見過ごされていることに対して問題を提起し、選挙権を行使できるよう活動する。
3 市が主催するイベントや地域のお祭りの機会を通じて、広く市民に対して障害への理解促進を働きかける。
4 勤務日の変更を提示され通院できなくなるため退職を考えているクライエントに、合理的配慮があることを説明する。
5 購入したばかりの高額商品のトラブルで困っている通院患者から依頼を受けて、消費生活センターにつなぐ。
1 生活に困窮して相談支援事業所を訪れた人に、生活困窮者自立支援事業の情報を提供する。
これは情報提供機能です。
2 投票に行けない人々が見過ごされていることに対して問題を提起し、選挙権を行使できるよう活動する。
これは発見機能です。
3 市が主催するイベントや地域のお祭りの機会を通じて、広く市民に対して障害への理解促進を働きかける。
これは教育・啓発機能です。
4 勤務日の変更を提示され通院できなくなるため退職を考えているクライエントに、合理的配慮があることを説明する。
これは情報提供機能です。
5 購入したばかりの高額商品のトラブルで困っている通院患者から依頼を受けて、消費生活センターにつなぐ。
これが正解、調整機能です。
次の記事
次は、ケアマネジメントについて。
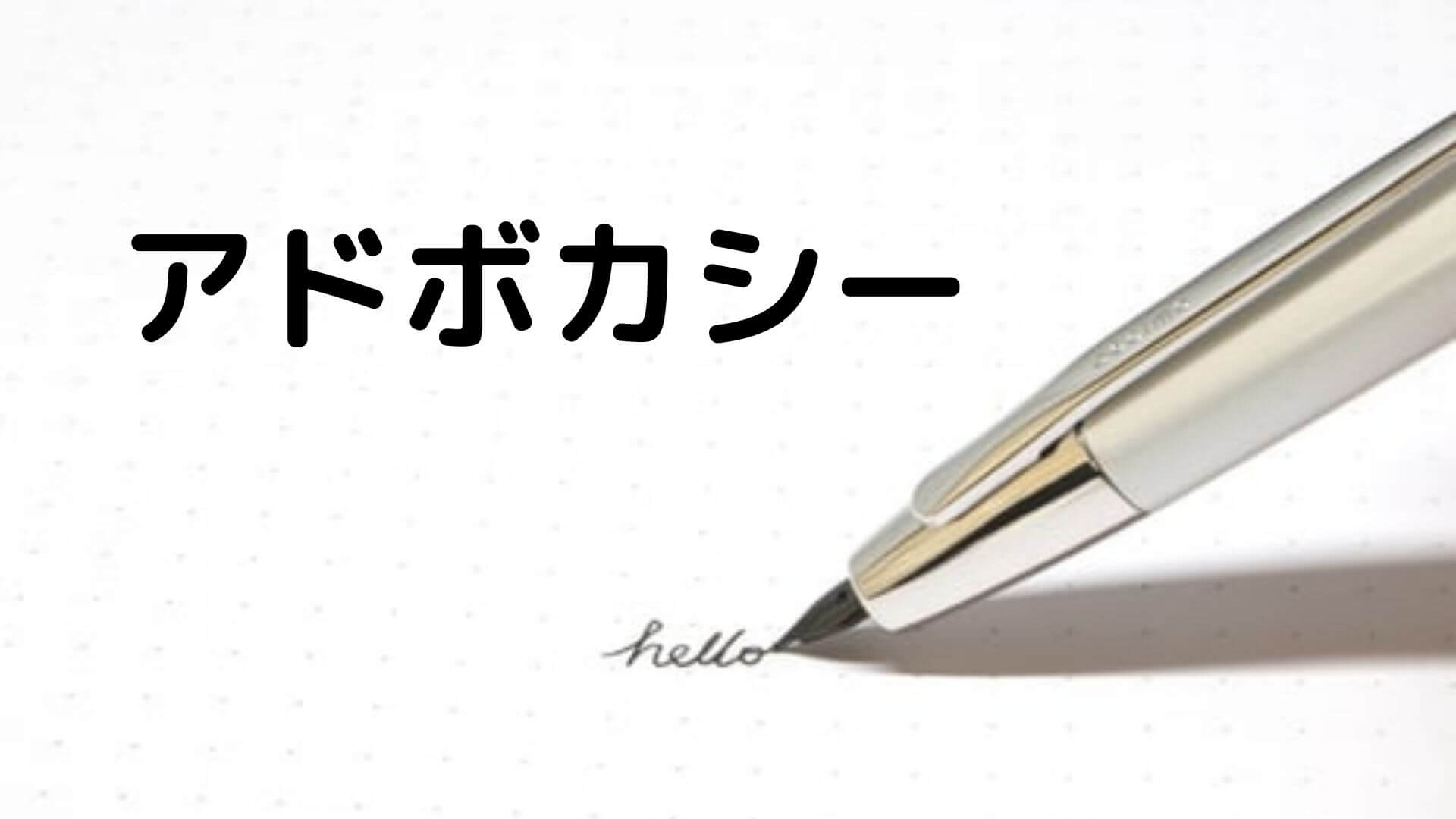


コメント