歴史
1899年、ドイツのクレペリンの「早発痴呆」が、現在の統合失調症の病態であると思われます。
1908年、スイスの精神医学者ブロイラー(Bleuler,E.)が「連想分裂も持った精神障害のグループ」としてスキゾフレニア(schizophrenia)を提案することによって早発痴呆という名称は廃止、「精神分裂病」と呼ばれるようになります。
2002年、日本精神神経学会で「精神分裂病」という病名は「統合失調症」に変更されました。
.png)
精神分裂病というと、多重人格(解離性障害)とイメージしてしまうかもしれないからね。
統合失調症の概要
ICD-10(国際疾病分類)の分類
ICD-10(国際疾病分類)によると「精神および行動の障害」はF群に分類され、統合失調症はその中のF2群に分類されます。
F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害:アルコールや薬物による障害
F2 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害:統合失調症など
F3 気分[感情]障害:躁うつ病など
F4 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害:不安障害、強迫性障害、解離性障害
F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群:摂食障害、非器質性睡眠障害、性機能不全など
F6 成人の人格及び行動の障害:人格障害、性同一性障害、性嗜好の障害など
F7 知的障害〈精神遅滞〉:知的障害など
F8 心理的発達の障害:発達障害など
F9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害:多動性障害、行為障害、チック障害など
原因
厚生労働省「みんなのメンタルヘルス 総合サイト」によると、統合失調症の原因はよくわかっていないとのことです。
脳内で情報を伝える神経伝達物質のバランスが崩れることが関係しているとか、大きなストレスが関係しているとか、遺伝子も関与しているとか、いろいろ言われていますが、統合失調症になりやすい要因をいくつか持っている人が、仕事や人間関係のストレスによって発症するのではないかと考えられています。
症状
統合失調症の症状は「陽性症状」と「陰性症状」に分けることができます。
陽性症状は健康なときにはなかった状態が表れるもの、陰性症状は健康なときにあったものが失われるものです。
陰性症状:意欲の低下、感情鈍麻等
統合失調症では陽性症状(幻覚、妄想、精神運動興奮、昏迷など)と陰性症状(抑うつ、無気力、ひきこもり、倦怠感、感情の平板化)があります。陽性症状としては、考えがまとまらない滅裂思考、思考の進行が急に停止する思考途絶、体に実際に感じる体感幻覚、自分の意思に反して誰かに考えや体を支配され操られていると感じる作為体験、考えていることが声となって聞こえてくる考想化声、自分の考えが他者に筒抜けになっていると感じる考想伝播、自分の考えが抜き取られて消えたように感じる考想奪取、などがあります。
統合失調症の妄想の特徴は、その原因が特定できない一次妄想です。一次妄想には、何か大きな事件が起こりそうな予感を持つ妄想気分、突然あるアイデアが思いつきそのまま確信される妄想着想、突然ある知覚に対して特別な意味づけがなされ、そのまま確信される妄想知覚があります。
.png)
考想化声、考想伝播、考想奪取、作為体験などはシュナイダーの一級症状と呼ばれていて、一次妄想とシュナイダーの一級症状があれば、統合失調症を真っ先に疑うべきだよ。
ICD-10では以下の4項目が診断基準になっています。
・ 操られる、影響される、抵抗できないという妄想。妄想知覚(知覚した日常の現象から、直ちに妄想的な意味を感じる(例:白衣についた小さな血痕を見て、「自分は死ぬ運命だ」と確信するなど)
・自分の行動に絶えずコメントしたり(例:食べようとすると「食べるな」と聴こえてくる)、仲間たちが自分を話題にしたりする幻聴。身体のある部分から発せられる幻聴(例:お腹から聴こえてくる)
・文化的に不適切で全くありえない内容の持続的な妄想(例:自分は万能の神であり世界平和のため永遠の命を持っているなど)
以上のうち1つが1ヶ月以上続いていること、ただし他の脳の疾患や薬物に関連した精神障害ではないことを確認し診断します。
DSM-5では、以下のような診断基準となっています。
(1)妄想
(2)幻覚
(3)まとまりのない発語(例:頻繁な脱線または滅裂)
(4)ひどくまとまりのない、または緊張病性の行動
(5)陰性症状(情動表出の減少、意欲欠如)
治療
統合失調症の治療には、薬物療法と非薬物療法があり、両者を組み合わせて行うことが一般的です。
薬物療法としては抗精神病薬で中心となる症状を抑え、補助的に抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、気分安定薬などが組み合わせられます。
薬によって完治することはないので、専門医の判断で量を調整したりしながら、気長に治療を続けます。
.png)
症状が安定していても、自己判断で薬を止めたりすることはNGだよ。
非薬物療法としては心理社会的な治療(専門家と話をしたりリハビリテーションを行う治療)があります。
心理社会的な治療には、心理教育や生活技能訓練(SST)、作業療法があります。
生活技能訓練(SST):ロールプレイ等を通じて、社会生活や対人関係のスキルを回復する訓練を行う
作業療法:園芸、料理、木工などの軽作業を通じて、生活機能の回復を目指す
.png)
重篤な統合失調症の治療には、「修正型電気けいれん療法」があるよ。薬物療法ができない妊婦さんにも使えるよ。
過去問
第17回 問題3
統合失調症に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 幻覚をしばしば認める。
2 見当識障害がある。
3 意識障害がある。
4 血液検査で診断できる。
5 ICD-10によれば、F3群に分類される。
1 幻覚をしばしば認める。
正しいです。幻覚は陽性症状として見られます。
2 見当識障害がある。
間違いです。見当識障害は認知症や高次脳機能障害などでよく見られる症状で、自らの置かれている環境を理解する能力(見当識)の障害です。
3 意識障害がある。
間違いです。
4 血液検査で診断できる。
間違いです。
5 ICD-10によれば、F3群に分類される。
間違いです。ICD-10ではF2群に分類されています。
F3群は感情障害です。
第25回 問題3
次のうち、統合失調症の陰性症状として、正しいものを1つ選びなさい。
1 言葉のサラダ
2 貧困妄想
3 感情鈍麻
4 作為体験
5 思考抑制
選択肢3が正解です。選択肢1の言葉のサラダは陽性症状の一種で、まとまりのない言葉をつなげただけの意味の通らない言動を指します。
第21回 問題9
次のうち、統合失調症の非薬物的治療法として、最も用いられているものを1つ選びなさい。
1 理学療法
2 作業療法
3 内観療法
4 曝露療法
5 精神分析療法
選択肢2が正解です。
第17回 問題7
統合失調症に対する抗精神病薬による治療に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1 幻覚・妄想より認知機能障害に有効である。
2 高齢者に対しては、若年者より投与量を増やす。
3 症状寛解後も長期にわたる服薬を要する。
4 薬剤選択に当たっては、糖尿病の合併を考慮する。
5 多剤併用を基本とする。
1 幻覚・妄想より認知機能障害に有効である。
間違いです。
2 高齢者に対しては、若年者より投与量を増やす。
間違いです。
3 症状寛解後も長期にわたる服薬を要する。
正しいです。
4 薬剤選択に当たっては、糖尿病の合併を考慮する。
正しいです。非定型抗精神病薬は、高血糖を生じさせることがあり、特にオランザピンとクエチアピンは糖尿病患者への投与は禁忌です。
5 多剤併用を基本とする。
間違いです。副作用等を考えると多剤併用はいけません。
第24回 問題6
- 次の記述のうち、予後がよいと推測される統合失調症の特徴として、適切なものを2つ選びなさい。
1 解体型の病型である。
2 緩徐に発症する。
3 若年で発症する。
4 発症に明らかな誘因がある。
5 発症してから未治療の期間が短い。
選択肢4と5が正解です。
第25回 問題9
- 統合失調症の維持期における治療に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
1 医療者は、患者と治療のゴールや内容について話し合い、決定できるよう支援する。
2 抗精神病薬の服用は、患者本人の判断に委ねる。
3 入院による治療を優先的に行う。
4 患者の再発予防のため、家族への心理教育を行う。- 5 病状悪化のきっかけになるので、患者が希望しても就労はしないよう助言する。
選択肢1と4が正解です。
第26回 問題6
- Cさん(26歳、男性)は、仕事上のささいなミスを上司に注意されてから、職場の雰囲気が変わったように感じ、漠然とした不安を抱くようになった。通勤の時の風景もいつもと違って見え、何か不吉なことが起きるのではないかと怖くなって外に出ることができなくなった。自室にひきこもってさかんに、「怖い」と訴えるため、心配した両親に連れられて精神科を受診した。
次のうち、Cさんの精神症状として、正しいものを1つ選びなさい。
1 関係妄想
2 妄想気分
3 罪業妄想
4 抑うつ気分
5 広場恐怖
選択肢2が正解です。この事例は、原因が特定できない一次妄想の一種である妄想気分の症状です。
第26回 問題45
- 次のうち、統合失調症の再発率を高めるとされる家族の状況として、適切なものを1つ選びなさい。
1 共依存
2 イネイブリング
3 高い感情表出
4 投影性同一視- 5 逆転移
選択肢3が正解です。高い感情表出を「高EE(High Expressed Emotion)」と呼び、精神疾患の患者に対して家族や医療従事者が強い感情表出をすることを指します。統合失調症では「高EE家族」がいると再発率は高まります。
次の記事
次は、気分障害について。
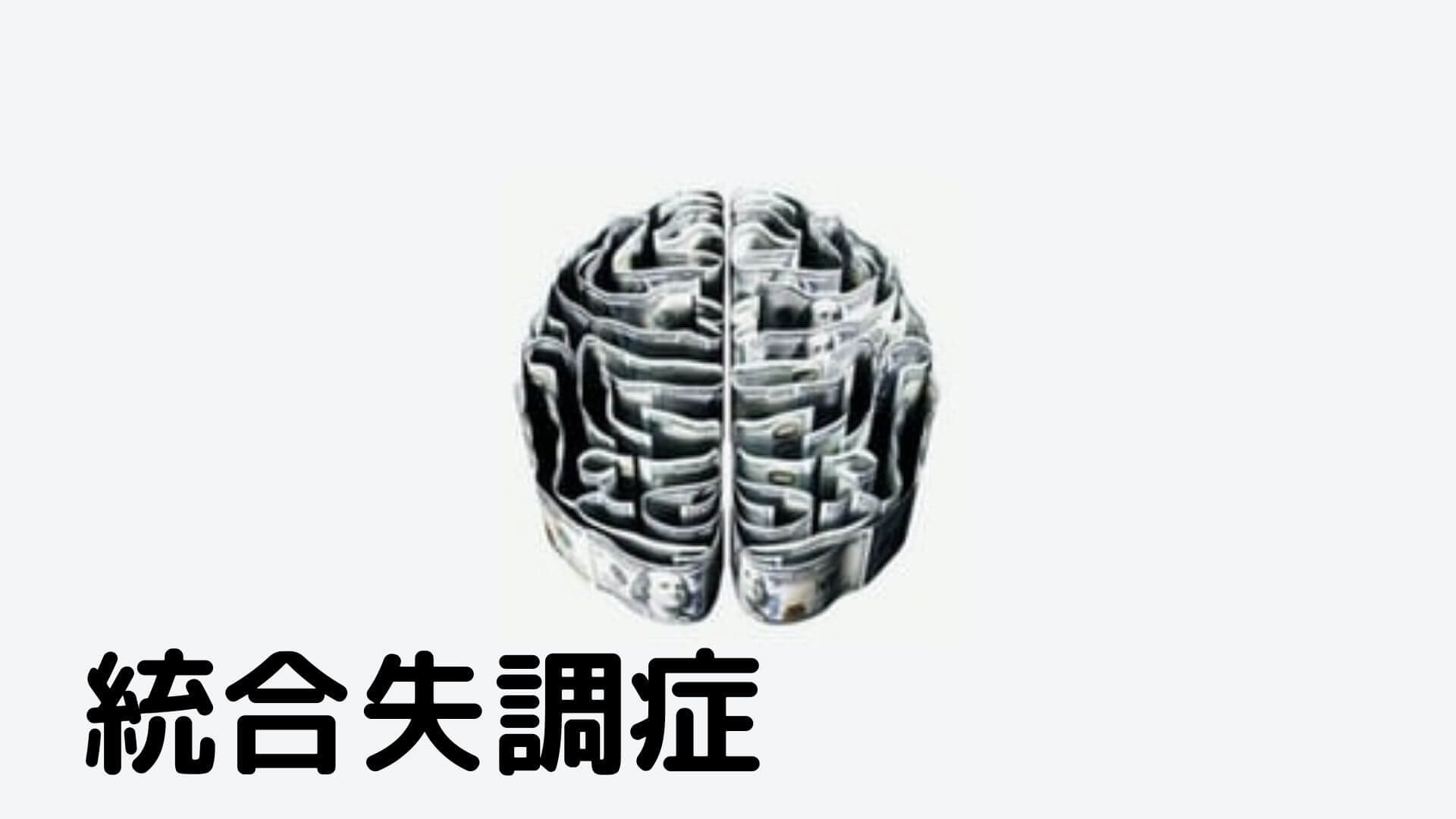



コメント