精神保健福祉士国家試験には、「国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)の倫理綱領」が出題されます。
国際ソーシャルワーカー連盟( IFSW )の倫理綱領
「倫理基準」は以下4つの倫理責任が規定されています。
Ⅰ.利用者に対する倫理責任
①利用者との関係
②利用者の利益最優先
③受容
④説明責任
⑤利用者の自己決定の尊重
⑥利用者の意思決定能力への対応
⑦プライバシーの尊重
⑧秘密の保持
⑨記録の開示
⑩情報の共有
⑪性的差別、虐待の禁止
⑫権利侵害の防止
Ⅱ.実践現場における倫理責任
①最良の実践を行う責務
②他の専門職等との連携・協働
③実践現場と綱領の遵守
④業務改善の推進
Ⅲ.社会に対する倫理責任
①ソーシャル・インクルージョン
②社会への働きかけ
③国際社会への働きかけ
Ⅳ.専門職としての倫理責任
①専門職の啓発
②信用失墜行為の禁止
③社会的信用の保持
④専門職の擁護
⑤専門性の向上
⑥教育・訓練・管理における責務
⑦調査・研究
.png)
精神保健福祉士の倫理綱領はほとんど出題されないので、あまり見ないでいいよ。
精神保健福祉士の倫理綱領
前 文
われわれ精神保健福祉士は、個人としての尊厳を尊び、人と環境の関係を捉える視点を持ち、共生社会の実現をめざし、社会福祉学を基盤とする精神保健福祉士の価値・理論・実践をもって精神保健福祉の向上に努めるとともに、クライエントの社会的復権・権利擁護と福祉のための専門的・社会的活動を行う専門職としての資質の向上に努め、誠実に倫理綱領に基づく責務を担う。
目 的
この倫理綱領は、精神保健福祉士の倫理の原則および基準を示すことにより、以下の点を実現することを目的とする。
1.精神保健福祉士の専門職としての価値を示す
2.専門職としての価値に基づき実践する
3.クライエントおよび社会から信頼を得る
4.精神保健福祉士としての価値、倫理原則、倫理基準を遵守する
5.他の専門職や全てのソーシャルワーカーと連携する
6.すべての人が個人として尊重され、共に生きる社会の実現をめざす
倫理原則
1.クライエントに対する責務
(1)クライエントへの関わり 精神保健福祉士は、クライエントの基本的人権を尊重し、個人としての尊厳、法の下の平等、健康で文化的な生活を営む権利を擁護する。
(2)自己決定の尊重 精神保健福祉士は、クライエントの自己決定を尊重し、その自己実現に向けて援助する。
(3)プライバシーと秘密保持 精神保健福祉士は、クライエントのプライバシーを尊重し、その秘密を保持する。
(4)クライエントの批判に対する責務 精神保健福祉士は、クライエントの批判・評価を謙虚に受けとめ、改善する。
(5)一般的責務 精神保健福祉士は、不当な金品の授受に関与してはならない。また、クライエントの人格を傷つける行為をしてはならない。
2.専門職としての責務
(1)専門性の向上 精神保健福祉士は、専門職としての価値に基づき、理論と実践の向上に努める。
(2)専門職自律の責務 精神保健福祉士は同僚の業務を尊重するとともに、相互批判を通じて専門職としての自律性を高める。
(3)地位利用の禁止 精神保健福祉士は、職務の遂行にあたり、クライエントの利益を最優先し、自己の利益のためにその地位を利用してはならない。
(4)批判に関する責務 精神保健福祉士は、自己の業務に対する批判・評価を謙虚に受けとめ、専門性の向上に努める。
(5)連携の責務 精神保健福祉士は、他職種・他機関の専門性と価値を尊重し、連携・協働する。
3.機関に対する責務
精神保健福祉士は、所属機関がクライエントの社会的復権を目指した理念・目的に添って業務が遂行できるように努める。
4.社会に対する責務
精神保健福祉士は、人々の多様な価値を尊重し、福祉と平和のために、社会的・政治的・文化的活動を通し社会に貢献する。
倫理基準
1.クライエントに対する責務
(1)クライエントへの関わり 精神保健福祉士は、クライエントをかけがえのない一人の人として尊重し、専門的援助関係を結び、クライエントとともに問題の解決を図る。
(2)自己決定の尊重
a クライエントの知る権利を尊重し、クライエントが必要とする支援、信頼のおける情報を適切な方法で説明し、クライエントが決定できるよう援助する。
b 業務遂行に関して、サービスを利用する権利および利益、不利益について説明し、疑問に十分応えた後、援助を行う。援助の開始にあたっては、所属する機関や精神保健福祉士の業務について契約関係を明確にする。
c クライエントが決定することが困難な場合、クライエントの利益を守るため最大限の努力をする。
(3)プライバシーと秘密保持精神保健福祉士は、クライエントのプライバシーの権利を擁護し、業務上知り得た個人情報について秘密を保持する。なお、業務を辞めたあとでも、秘密を保持する義務は継続する。
a 第三者から情報の開示の要求がある場合、クライエントの同意を得た上で開示する。クライエントに不利益を及ぼす可能性がある時には、クライエントの秘密保持を優先する。
b 秘密を保持することにより、クライエントまたは第三者の生命、財産に緊急の被害が予測される場合は、クライエントとの協議を含め慎重に対処する。
c 複数の機関による支援やケースカンファレンス等を行う場合には、本人の了承を得て行い、個人情報の提供は必要最小限にとどめる。また、その秘密保持に関しては、細心の注意を払う。
クライエントに関係する人々の個人情報に関しても同様の配慮を行う。
d クライエントを他機関に紹介する時には、個人情報や記録の提供についてクライエントとの協議を経て決める。
e 研究等の目的で事例検討を行うときには、本人の了承を得るとともに、個人を特定できないように留意する。
f クライエントから要求がある時は、クライエントの個人情報を開示する。ただし、記録の中にある第三者の秘密を保護しなければならない。
g 電子機器等によりクライエントの情報を伝達する場合、その情報の秘密性を保証できるよう最善の方策を用い、慎重に行う。
(4)クライエントの批判に対する責務 精神保健福祉士は、自己の業務におけるクライエントからの批判・評価を受けとめ、改善に努める。
(5)一般的責務
a 精神保健福祉士は、職業的立場を認識し、いかなる事情の下でも精神的・身体的・性的いやがらせ等人格を傷つける行為をしてはならない。
b 精神保健福祉士は、機関が定めた契約による報酬や公的基準で定められた以外の金品の要求・授受をしてはならない。
2.専門職としての責務
(1)専門性の向上
a 精神保健福祉士は専門職としての価値・理論に基づく実践の向上に努め、継続的に研修や教育に参加しなければならない。
b スーパービジョンと教育指導に関する責務
1)精神保健福祉士はスーパービジョンを行う場合、自己の限界を認識し、専門職として利用できる最新の情報と知識に基づいた指導を行う。
2)精神保健福祉士は、専門職として利用できる最新の情報と知識に基づき学生等の教育や実習指導を積極的に行う。
3)精神保健福祉士は、スーパービジョンや学生等の教育・実習指導を行う場合、公正で適切な指導を行い、スーパーバイジーや学生等に対して差別・酷使・精神的・身体的・性的いやがらせ等人格を傷つける行為をしてはならない。
(2)専門職自律の責務
a 精神保健福祉士は、適切な調査研究、論議、責任ある相互批判、専門職組織活動への参加を通じて、専門職としての自律性を高める。
b 精神保健福祉士は、個人的問題のためにクライエントの援助や業務の遂行に支障をきたす場合には、同僚等に速やかに相談する。また、業務の遂行に支障をきたさないよう、自らの心身の健康に留意する。
(3)地位利用の禁止 精神保健福祉士は業務の遂行にあたりクライエントの利益を最優先し、自己の個人的・宗教的・政治的利益のために自己の地位を利用してはならない。また、専門職の立場を利用し、不正、搾取、ごまかしに参画してはならない。
(4)批判に関する責務
a 精神保健福祉士は、同僚の業務を尊重する。
b 精神保健福祉士は、自己の業務に関する批判・評価を謙虚に受けとめ、改善に努める。
c 精神保健福祉士は、他の精神保健福祉士の非倫理的行動を防止し、改善するよう適切な方法をとる。
(5)連携の責務
a 精神保健福祉士は、クライエントや地域社会の持つ力を尊重し、協働する。
b 精神保健福祉士は、クライエントや地域社会の福祉向上のため、他の専門職や他機関等と協働する。
c 精神保健福祉士は、所属する機関のソーシャルワーカーの業務について、点検・評価し同僚と協働し改善に努める。
d 精神保健福祉士は、職業的関係や立場を認識し、いかなる事情の下でも同僚または関係者への精神的・身体的・性的いやがらせ等人格を傷つける行為をしてはならない。
3.機関に対する責務
精神保健福祉士は、所属機関等が、クライエントの人権を尊重し、業務の改善や向上が必要な際には、機関に対して適切・妥当な方法・手段によって、提言できるように努め、改善を図る。
4.社会に対する責務
精神保健福祉士は、専門職としての価値・理論・実践をもって、地域および社会の活動に参画し、社会の変革と精神保健福祉の向上に貢献する。
過去問
第21回 問題22
25年のキャリアを持つA精神保健福祉士は、クライエントの照会を通じて知り合った経験 3 年目の精神保健福祉士から、「3年目になったが、まだ適切な支援ができない」と相談を受けた。
A精神保健福祉士は、以前にも他の中堅の精神保健福祉士から、「経験は増えたが、仕事の達成感を得にくい」と相談を受けていた。
そこで、キャリアに応じた仕事の仕方や目標を整理するためのグループ形式の研修会を開催した。
参加者からは、「経験年数に合わせた支援方法や目標が具体的となった」、「モチベーションが上がった」といった好評が得られた。
A精神保健福祉士が開催した研修会のねらいとして適切なものを、次の国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)の倫理綱領に規定されている倫理基準から2つ選びなさい。
1 業務改善の推進
2 情報の共有
3 専門性の向上
4 専門職の擁護
5 専門職の啓発
正解は選択肢1と3です。
第20回 問題22
次の記述のうち、国際ソーシャルワーカー連盟( IFSW )の倫理綱領の「倫理基準」に関するものとして、正しいものを1つ選びなさい。
1 専門職としての倫理責任として、秘密の保持が示されている。
2 利用者に対する倫理責任として、説明責任が示されている。
3 実践現場における倫理責任として、専門職の擁護が示されている。
4 社会に対する倫理責任として、業務改善の推進が示されている。
5 専門職としての倫理責任として、社会への働きかけが示されている。
1 専門職としての倫理責任として、秘密の保持が示されている。
間違いです。秘密の保持は「利用者に対する倫理責任」です。
2 利用者に対する倫理責任として、説明責任が示されている。
これが正解です。
3 実践現場における倫理責任として、専門職の擁護が示されている。
間違いです。専門職の擁護は「専門職としての倫理責任」です。
4 社会に対する倫理責任として、業務改善の推進が示されている。
間違いです。業務改善の推進は「実践現場に対する倫理責任」です。
5 専門職としての倫理責任として、社会への働きかけが示されている。
間違いです。社会への働きかけは「社会に対する倫理責任」です。
第16回 問題22
次の記述のうち、日本精神保健福祉士協会倫理綱領の目的に規定されているものとして、正しいものを1つ選びなさい。1 他の専門職や全てのソーシャルワーカーと連携する。2 客観的証拠に基づいた実践を展開する。3 専門職としての知識・技術を理解する。4 所属機関と地域社会から信頼を得る。5 福祉と平和に満ちた社会を形成する。
選択肢1が正解です。
次の記事
次は、ソーシャルワーク専門職の属性について。
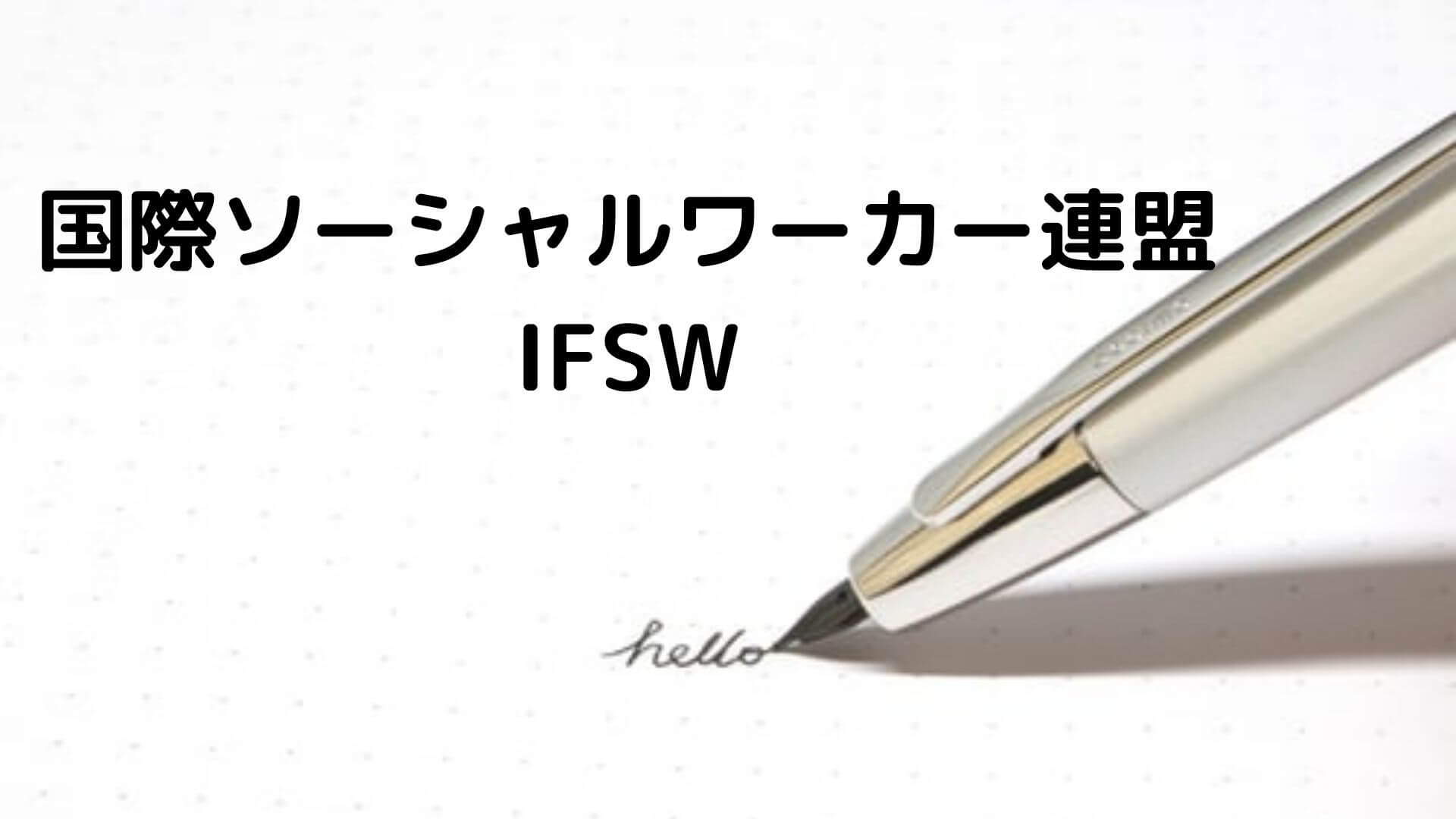



コメント